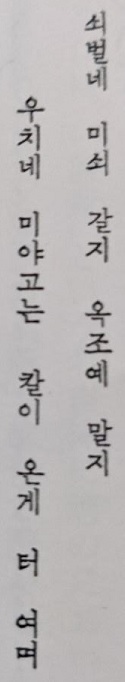日本は唐に支配されていた
白村江の戦い後、倭は唐の支配を受けていた可能性が高いという、通史には出てこない隠された歴史が見えてくることは先にも述べた。
それは、「藤原」という名自体に唐のにおいがすることからも推察されよう。藤原の「藤」は音で読むとトウ、つまり「唐」の音と同じなのである。
以下その支配の模様を追っていくことにしよう。
遣唐使について
 |
| 遣唐使船 |
遣唐使は、日本人が唐の文化や政治の仕組みを学ぶために送ったものだといわれている。しかし白村江の戦い後、日本にはすでに唐の勢力が入ってきているというのなら、
わざわざ文化や政治を学びに唐に渡るということはおかしくないだろうか。以上のことをふまえたうえでもう一度遣唐使というものを見てみよう。
遣唐使船は幅広い船体、大きな船首尾の反り、二本の帆柱に網代帆の帆装、船首の碇捲き上げ用の轆轤など、
唐型の船で、さらに、日本の港から唐の港へ行くには、年に一度の季節風を利用して片道数ヵ月もかかるのである。にもかかわらず、
日本からの留学僧として唐に渡った最澄、空海などが、わずか一年や二年で漢字、
梵字をマスターして帰国しているというのはおかしいのではないだろうか。
これらのことから結局遣唐使とは、日本を統治するためのブレーンを唐本国が一方的に送り込んだものであって、最澄、空海などもその例外ではなかったのだろうと考えられている。
豆知識 「冬至」と「夏至」
「冬至」といえば、現在では柚子湯を立てて入浴することを思い浮かべるが、なぜ「冬至」というのであろうか。
その理由として昔、日本から唐に行くには蒸気機関が発明される以前まで、北東からの風が吹く冬の季節しか航行して行けなかった。
だからこれは「唐至」の意味で、「冬至」とはそこから命名された当て字であるという。
また「夏至」は、「ゲシ」と現在読まれるが、「夏」の文字で「ゲ」の訓読みはない。これは、当時の唐の人間からみれば日本は地の果ての外地であり、
その日本へは年に一度、夏にしか渡海できないことから、「夏至」は「外至」の無理やりの当て字と考えられる。
|
漢字について
白村江の戦い後、郭務悰が全国に「則天(漢)唐字使用令」を布令し、その漢字を強制的に定着させようとして八二一年につくられたのが勧学院であったという。
さらに、漢字を読むための補助的な道具としてわが国独自に発明されたとする「訓点」と送りがなのカタカナも、実は唐が日本に押しつけたという説もある。
「万葉集」について
通史では、八世紀後半に、大伴家持らによって編さんされ、わが国最古の歌集とされている「万葉集」。
この書物の文学的な評価は別にして、ここでは少し違った視点でこの書物を見てみたい。
| 一、 | 万葉集で使われている万葉仮名は漢字の羅列つまり漢文であるが、
この一字一字を細かく見ていくと古代韓国語で読むことができる。 |
| 二、 | 万葉集の歌の中には、古代中国の影響が見られる。 |
一、二のことについて、巻一の七番歌(額田王の歌)を例にとって見てみよう。
まず、一について、
| (万葉仮名) | 金野乃 美草苅葺 屋杼礼里之
兎道乃宮子能 借五百磯所念 |
| 従来の解釈 | 秋の野の み草刈り葺き 宿れりし
宇治の都の 仮いほし思ほゆ |
| (秋の野の萱を苅って屋根に葺き、旅宿りした宇治の都の仮のいおりが思われる) |
古代韓国語による解釈
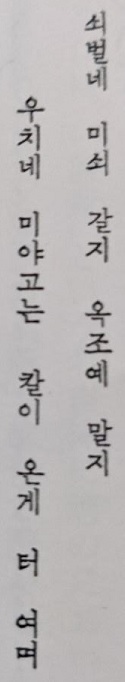 |
古代韓国語
解釈 |
左下「古代韓国語解釈」参照
(新羅は刀を磨いて戦いに備えている。締め苦しめないといいのに・・・吾がお上の百済の都は敵がおそってくるから、陣地をお固めなされ)
次の二について、「金野乃」の「金」を「アキ」と、発音させるところに、古代中国の五行説の影響が見られる。
なぜ日本古来の「万葉集」が古代韓国語で読めたり、唐の影響が顔をのぞかせるのであろうか。
韓国に残る「新羅郷歌」を唐勢力が奪いとり、唐詩化つまり漢文化して、唐からの派遣官吏が日本へ持ち込み、
「日本書紀」に出てくる人の名を適当につけて「万葉集」としたのだという説がある。それが、唐からの進駐軍の後裔である公家、
藤原氏によってひろめられたが、完全に倭国にあう文章にはできなかったので、古代韓国語で読めたり、唐の影響を受けていたりするのだというのである。
今日、日本最古とされている文学書「万葉集」も、真の歴史を隠す一つの道具だったのかもしれない。
支配されていた先住日本人
 |
| ねぶた祭り |
唐の占領軍が入ってきた時に山に逃げ込んだわが国の人々が、山窩と呼ばれるようになった。
そして逃げ遅れた人や、逃げ込んでも見つかった人は、唐勢力の手によってかなり酷い扱いをされていたらしい。
たとえば、唐勢力は、敗走する彼らを谷底へ追い込んで、穴へ生き埋めにした。しかもその穴は、彼ら自らが掘ったもので、
それを踏み固めた人々は、埋められた人たちの身内だったという。これが今日、東北三大祭の一つとして、土を踏み固める格好をして踊る「ねぶた祭り」のルーツであるらしい。
「先住民は「根」であるから「蓋」をしてしまえ(根からむしりとって蓋をするの意)」ということからその奇妙な名前がついたという。
さらに、東大寺大仏鋳造の時にも、奴隷として虫ケラのように扱われていたのである。逃亡を防ぐため、互いに一微の樹皮でつながれていたから、
一人が足をすべらせると皆次々と煮えたぎる大きな坩堝の中へ転落した。屍を街路へ放り出される者よりも、
黒焦げになり灰になって撒かれた者のほうが多かったという。
唐勢力に、「大仏様建立のための落命は、極楽往生する」といわれても、「極楽往生」などは、とても信じることのできない生き地獄だったようである。
藤原氏
藤原氏の「藤」は音で読むとトウ、つまり「唐」の音と同じなのである。唐という国は、その支配領域がユーラシア大陸を、
西は中央アジア、アラル海、南はベトナムにまでおよぶ大帝国であり、文化度、軍事力、資源力、どれをとっても当時、右にでるものはいないといわれるほどの、
世界的な大国であった。
この唐という強大すぎる帝国の前に、わが国の人たちは抵抗するすべを知らなかったであろう。一方的に唐のなすがままになるしか道はなかったとしか考えられない。
そして唐勢力の藤原氏は、この強大な唐帝国をバックに貴族という特権階級を作り、日本中の荘園を我がものにして、栄華を誇ったのであった。
「この世をば…」と詠んだ藤原道長はその極めつけであろう。
権力者の最後
敗戦国百済の人間で、唐では朝散大夫という決して高いとはいえない身分の郭務悰が、倭においては絶大な権力をふるい、
神以上の存在として君臨していたらしいということは先にも述べた。だが人間、こうした環境において「自惚れ」というしがらみに足をとられることがたびたびある。
もし、郭務悰と鎌足が同一人物だったとすると、彼らも「自惚れ」で身をほろぼす例にもれることがなかったとすれば、真の歴史の説くところの彼らの最後は、
意外と無残なものであったのかもしれない。
また、この後に権力を握る不比等が、鎌足の子であるという事実にも疑問をさしはさむことができる。
通史では皇統は、七世紀後半に起こった壬申の乱を契機に天智系から天武系に代わったとされるのだが、これを鎌足のあと、
不比等に権力が移り変わったことを示すという大胆な仮説をうちたてることもできるのではないだろうか。つまり、鎌足の後に権力を握った不比等が、
実は鎌足の子供ではなく、全く血のつながっていない人間だというのである。そう考えていくと、やはり鎌足の最後は通史とは全く異なり、
床の上での臨終ではなかった可能性が非常に高い。
真相をまとめると、
「郭務悰は中臣鎌足であり、歌人の額田王をそばに侍らせて、天智天皇を名乗り倭国の王になろとするが、これが唐の反感を買い殺される。
次の使者である新羅の不比等(不比等は新羅の人間である)も、唐の反感を買って殺される。そして、三番目の使者である唐の麻呂が藤原氏の始祖となる。
また、天武天皇は実在しない。よって壬申の乱は架空の出来事である。」
このようになると思われる。
明治まで・・・
その後も唐は、日本を完全に勢力圏内におくための工作を着々と進めていったと考えられる。そして、唐本国から送り込まれたさまざまな人間のあいだで、
権力の奪い合いが行われながら、藤原氏という枠のなかで、多くの流れが徐々に一つの流れになっていったと考えることができる。藤原四子といわれる人々が活躍した時代も、
さまざまな勢力の争いがあったと考えられよう。時の為政者が自らを正当化するために行った歴史の改竄なども、
数えてみれば切りのないことだったろう。
こうした日本国内の唐勢力は、九〇七年唐本国が契丹によって滅ぼされた後も「藤(藤原)」つまり、公家として残っていった。中世以降も平氏をはじめ、
武家におされて一時その勢力を弱められたものの、政治面では摂関の職を独占して天皇家とのむすびつきを強くし、
文化面でも和歌が珍重されたり、室町時代には金閣寺・銀閣寺といった繊細かつ優美な建築物が見られるなど、公家文化としての唐のいぶきが強く感じられるのである。
さらに江戸時代末期から明治時代初期にかけても唐を滅ぼした契丹民族が開発した平仮名よりも、
唐の則天文字(漢字)を読み易くするために作られた訓点に由来するカタカナが好んで使用されたようであり、
公家としての唐勢力は、この時期まで脈々と生き続けたのである。
|
真実を求めて
過去から現代に至るまで、一国を左右するほどの重大な政治事件は、歴史上表立って書かれていないということを念頭に、我々は歴史を見ていかねばならない。
ましてや、ほんの一握りの人間しか文字を読むことができなかった当時のわが国において、それまでのさまざまな記録を書き換えることなどは、思いのままだったと考えられる。
今回の歴史の探求は「現存する歴史は、その体制の維持を正当化するために書かれてきた虚構である」という仮定のもとにはじまった。
そうして見えてきたのは、わが国の人々は極めて長い年月にわたって、被支配的な立場におかれていたという歴史である。
このような歴史が、今日「異質な国家」として、世界中から批判を集めている日本という国の特質ができ上がった背景を物語っているような気はしないだろうか。
歴史の真実は、こうして何のこだわりもなく歴史を見ていくことで、案外浮き彫りにされるものなのかもしれない。
|
トップページへ戻る