平家の由来
平氏のおこりには諸説があるが、桓武天皇の曾孫高望王から始まるとする系図が疑わしいものであることは、
多くの学者も認めるところである。
「その一門公卿十六人、殿上人三十人余・・・、領封は日本国の半数を越える」という有様でありながら、危急存亡の
非常事態にどこからも誰も参集しない。何十万という兵が進軍する時も家臣団の名前は一つも出てこない。源氏の様に
各地から蜂起することもなく、福原港だけから何万という兵士が急に現れて進撃する。しかも有名な平家の公達の多くは
出生がはっきりしていないのである。平氏とは一体何なのか。
「平」とはペルシャの意味で、本来はタイラと言わず、ペイと呼んでいた。崇神朝や桓武朝とはまた系統の違う
ペルシャ系で、日本に入って来た時期も違う。
日本人はもともと多数の民族が混血しあってできているが、正倉院の御物などからもわかる様に、潮流の関係で
ペルシャなど西方から日本にたどり着くのは容易だったようだ。簡単な筏でも、黒潮に乗れば容易に日本に着くことは、
近年の東南アジアのボートピープルからもわかるであろう。
当時、イラン・イラクやエジプト・インドを含む、西方から流れ着いた碧眼の外国人は皆、京堀川や福原、敏馬などの
囲地に入れられ、日本の習慣や言葉を覚えてから、僧にならない者には平姓が与えられたのだという。いわば、
「平」とは外国人登録証のようなものだったと考えられる。源氏の様にどこそこの誰(例・木曽義仲)という呼び方が
無いのは、皆「平」という登録証のついた外国人部隊だったからかもしれない。
 豆知識 白瑠璃碗 豆知識 白瑠璃碗
口径12.0cm 高8.5cm
やや褐色を帯びた透明の碗形ガラス器
厚手のカットグラスは、ササン朝ペルシャ(二二六〜六五一)の領域にあたるイラン・イラクをはじめ、カスピ海沿岸、
中央アジア、中国などの遺跡からも出土している。おそらくイラン北部のギラーン州辺りで製作され、古墳時代後期に
日本に運ばれ、後、正倉院に納められたものであろう。ペルシャからのガラス器は、陸路でなく、船で海路により
伝来したと考えられる。ペルシャと古代日本のつながりを示すものである。
|
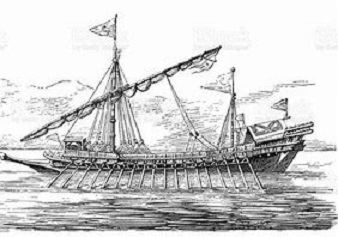 |
トルコのガレリー船
多数の櫂を奴隷に
漕がせた |
 |
| トルコのストレー |
 |
| 厳島神社 |
平家が、ペルシャ系であることを示すものは多い。
厳島神社宝物殿に残る「平家御一門座船」は、日本には類のないガレリー船であり、「平家公達の佩刀」は、いわゆる
日本刀ではなくセルジューク・トルコのストレー(直刀)という棒剣に似ている。さらに、平家が愛用した楽器も
ベイルートに同型のものがあり、平敦盛が吹いていたのは山羊の細い角笛で、中東のものである。
また、源平合戦にみられる「一騎打ち」は、それまでの日本や朝鮮にはなく、中近東やヨーロッパで用いられた
戦闘方式であり、平家が持ち込んだとされる。
豆知識 景清のコンタクト
大男で力が強く、屋島の合戦では敵の兜の錣を引きちぎったと言われる平家の侍大将、景清は、平家滅亡後、
頼朝の命を狙うために身を潜めた。目の上に魚のウロコを付けて変装し、京まで頼朝を追ったが暗殺に失敗して
捕らえられ、その時頼朝の顔を見るのが辛いと言って自ら両目を潰したという。
しかしこれは、碧眼を隠そうとして無理矢理ウロコを目の中に入れたために失明したのが真相ではないだろうか。
景清は今では、眼病の神様に祀られている。
|
  豆知識
赤旗 豆知識
赤旗
平家といえば赤旗、源氏といえば白旗であるが、「赤」は大陸から持ち込まれたとされている。化学染料の
ない当時、印度から渡ってきた蘇芳の実のさやから赤色染料を採っていた。黄色い花の咲く、豆科の植物である。
それは、後年、絵巻物に着色されたような鮮やかな紅ではなく、黒ずんだ赤色で、十メートルも離れると赤旗も黒く
見えたらしい。ともあれ、源平以来、わが国では紅白に分かれて対決するのが定着している。
|
トップページへ戻る
 豆知識 白瑠璃碗
豆知識 白瑠璃碗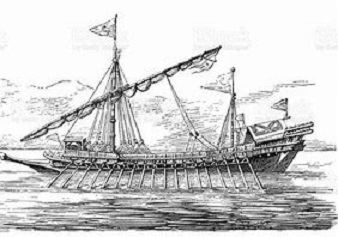



 豆知識
赤旗
豆知識
赤旗